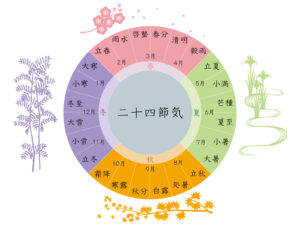処暑(しょしょ)

処暑(しょしょ):8月23日頃
「処」とは止まるという意味があり、処暑は暑さがなくなる、の意味です。
暑さの峠を越えて朝夕が涼しくなり、めっきり秋らしく過ごしやすい時季になります。
農作物の収穫が本格的に始まり、実りの秋が感じられます。
またこの頃から雨上がりや夜になると、美しい虫の声が聞こえ始めます。
毎日変化する小さな秋を探してみるのも楽しいですね。
⑴綿柎開(めんぷひらく)
8月23日~27日頃
「柎(はなしべ)」とは花の萼(ガク)を指し、
綿を包んでいる萼が開き始める頃の様子を表しています。
綿の花は7月〜9月にかけて薄黄色の美しい花を咲かせます。
その後50日ほど経つと実が熟し萼が弾けて、
白くてふわふわとした綿毛に守られていた種子が飛び出します。
この綿毛を紡いで木綿や糸や生地を作ります。
さらに、綿花を包んでいた種子からは綿実油が採取でき、
食用としても利用されています。
⑵天地始粛(てんちはじめてさむし)
8月28日~9月1日頃
「粛」とは鎮まる、弱まるという意味です。
8月の最終週を迎え、ようやく夏の暑さが収まり、全ての物事が改まるとされる時季です。
また、この頃は秋雨前線が到来するため、
北の方からゆっくりと南下しながらやってくる冷たい風が
秋の到来を肌で感じさせてくれます。
⑶禾乃登(こくものすなわちのぼる)
9月2日~7日頃
「禾(のぎ)」とは、稲や麦・粟など穀物の総称です。
大きく膨らんだ米粒の重みで稲穂がしだれる様子を示しています。
田んぼでは稲穂が黄金色に色づき収穫を目前に控える一方、
台風が多く発生する時季でもあり農家では対策に追われる日々を迎えます。
この季節の食べ物
カサゴ
高級魚の一つで、トゲだらけの風変わりな見た目とは裏腹に、
上品な味わいの白身が特徴です。
刺身にしても、焼いても煮ても美味しく、
塩焼きの残りの身に暑い湯をかけて骨湯にしても美味しくいただけます。
沿岸に生息するものは暗い褐色で、沖合のものは赤みがあります。
梨
店に並ぶと、秋の終わりを感じさせる果物です。
アジアやヨーロッパで食され、日本では明治以降に品種改良が活発に行われてきました。
もっとも多く生産されている「幸水(こうすい)」や、
程よい酸っぱさと甘さが調和している「豊水(ほうすい)」、
収穫量が少なく値段が高い「親水(しんすい)」などの品種があり、
梨三水と呼ばれる。
近年では上品な甘さが特徴の「二十世紀梨」も人気があります。
ヒラマサ
ブリ・カンパチとともにブリ御三家と呼ばれ、
その中でも最高峰とされる青背魚です。
色・形ともに、ブリに似ていますが、ブリと比べるとさっぱりとした味わいです。
地域によって「まさぎ」「びらそ」など、呼び方が異なります。
すだち
酸味が強すぎず、さっぱりとした爽やかな風味が特徴です。
旬は8月〜9月頃で、徳島県で多く生産されています。
かつては酢の代用品としても使われており、
鍋物や焼き魚などにかけて使われます。
クエン酸やビタミンcを多く含んでおり、美容に良いだけでなく、
疲労回復や風邪予防にも一役買います。
シマアジ
大衆魚であるアジの仲間で、
「幻の魚」と呼ばれるほど特に美味しいことから値段も張ります。
稚魚には黄色い横縞があることからこの名前がついたとされています。
旬は6月〜8月頃ですが、養殖されているものはほぼ1年中手に入ります。
冬が産卵期でその前に脂が乗ってくるので9月頃のものが特に美味しくいただけます。
さつまいも
長い年月をかけて中国から宮古島、九州へと渡り、
薩摩の芋として定着しました。
現在でも鹿児島県が生産量のトップとなっています。
さつまいもは地下に身をつけるため風害に強く、
1732年の享保の大饑餓を救うために徳川吉宗が関東にも広めました。
この季節の草花
ネムノキ
東北地方より南の山野に自生します。
樹高8mほどの落葉高木で、夏は羽状の葉を広げて緑陰を作り、
夕方になると葉が手を合わせたように折りたたまれます。
その葉の開閉の様子が、まるで眠りにつくように見えることからこの名前がつきました。
オシロイバナ
夏から秋にかけて開花する花。
漢字では「白粉花」とも書き、黒く丸い種を割ると、中から白い粉が出てきます。
江戸時代にはこの粉をおしろいの代わりに使ったという説もあります。
日の暮れかける夕方に咲くことから「夕化粧」と呼ばれることもあります。
ノウセンカズラ
中国原産の花で、初夏から初秋まで花を咲かせます。
古くから庭木として親しまれてきたつる植物です。
気根を出して木や壁などを這い登り、
夏の間濃いオレンジ色の鮮やかな花を咲かせ、人々の目を楽しませてくれます。
ホウセンカ
「鳳仙花」「爪紅」とも呼ばれる花です。
室町時代に伝わったとされる花で、インドやマレー地方など熱帯地方が原産です。
江戸時代以前はマニキュアのことを「爪紅」と読んでおり、
その材料は鮮やかな赤い花をもつホウセンカでした。
触れると弾ける果実も特徴です。
現在では品種改良もされており、赤や白、紫やピンクなど色とりどりの花を咲かせます。
コスモス
メキシコの高原が原産のキク科の花です。
江戸時代末期に日本に渡来し、明治時代に広く普及しました。
和名を「秋桜」「オオハルシャギク」と言い、
9月から10月にかけて白・桃・紅色などの花を咲かせます。
秋風に揺れる姿がなんとも言えずかわいらしいです。
この季節の生き物
ササゴイ
全長約52cmほどのサギの仲間です。
羽の上面は青藍色で、各羽の羽縁に白く縁取りがあり、
これが「笹の葉」に見えることからこの名前が付けられました。
川の近くなど水辺に生息しており、「キュウーッ」と
鋭い声で飛行しながら鳴くことが多いです。
虫や葉っぱを擬似餌にして魚を捕まえる賢さを持っています。
和亀
日本在来種のカメを「和亀」と言います。
代表的な「ニホンイシガメ」は自然破壊や外来種の増加によって絶滅危機に瀕しています。
9月から翌年4月頃に繁殖期を迎えます。
マツムシ
童謡『虫の声』にも登場する虫です。
平安時代には鳴く虫を籠に入れて音色を楽しむ遊びが流行りました。
松虫は「チロチロリン」、鈴虫は「リーンリーン」と聞こえますが、
当時は松虫と鈴虫の呼び名が逆で、江戸時代後期に初めて指摘されたそうです。
この季節の行事やオススメ
吉田の火祭り
8月26日・27日
夏の富士山の山じまいの祭りで、
富士山の登山シーズンを無事終えることに感謝を捧げます。
北口本宮富士浅間神社と諏訪神社の両社で行われます。
松明に火をつけると、町中が燃えるような迫力があります。
8月26日の鎮火祭と27日のすすき祭りの2日間行われ、
秋田県の「なまはげ柴灯祭」長野県の「御柱祭」に並ぶ、
日本三寄祭の一つとされています。
二百十日・二百二十日
9月1日頃・9月11日頃
立春から数えて210日目(9月1日)と220日目(9月11日)にあたる雑節です。
昔からこの頃は稲の開花とともに台風に襲われることが多かったため、
農家からは厄日とされてきました。
この時季、台風の被害から農作物を守り五穀豊穣を祈る「風祭り(かざまつり)」が各地で行われます。
おわら風の盆
9月1日〜3日頃
富山県八尾長で毎年行われる風祭りです。
1702年から始まったとされる歴史の長いお祭りで、
雑節の二百十日にあたる時季に風を鎮めて五穀豊穣を祈ります。
おわら節の囃子に乗って、
編笠に浴衣姿の艶やかな女踊りやはっぴ姿の勇ましい男踊りが行列を作り、
胡弓の調べとともに静かに踊ります。
written by はれる88