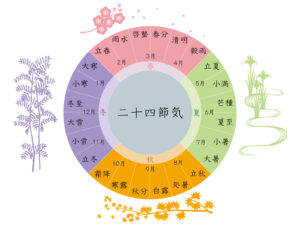立冬(りっとう)

立冬(りっとう):11月7日頃
「冬が立つ」の字の通り、暦の上では冬が始まります。
季節は冬型の西高東低に移ります。冷たい風が吹き始め、
日本海側では雪空が多く、太平洋側では冬晴れが多くなります。
陽の光が弱くなり、冬の気配を伺える頃です。
その年の一番初めに吹く強い北寄りの季節風を「木枯らし一号」と呼びます。
東京や大阪では立冬の頃に吹き始めることが多く、
冬の到来を示す自然現象の一つとされています。
「木枯らし」とは、強い風がひゅうひゅうと吹くたびに
木の葉が落ちて枯れることから付けられたそうです。
⑴山茶始開(つばきはじめてひらく)
11月7日~11日頃
ここでの「つばき」は2月頃に開花する「椿」ではなく
ツバキ科の「山茶花(サザンカ)」を指しています。
もともと中国ではツバキ科の花を総じて「山茶花(サンサカ)」というらしく、
サザンカはそこから変化したものとされます。
サザンカと椿は、どちらも天ぷらにして食べることができ、
淡白であっさりとした味わいが楽しめるそうです。
冬彼の景色の中で、
大輪の山茶花の花がより一層目立ちながら咲き誇る風景は、風情たっぷりです。
⑵地始凍(ちはじめてこおる)
11月12日~16日頃
夜の冷え込みが激しくなり、朝方にはいたるところに霜柱が立ちます。
地面が徐々に固く凍てつくようになります。
霜が降り、氷が張り、季節は冬を迎えます。
七十二侯はもともと中国の華北から伝わったものです。
華北は日本の東北地方とほぼ同じ緯度にあたるため、
寒気が南下すれば北日本の平野部でも雪が観測されることがあります。
⑶金盞香(きんせんかさく)
11月17日~21日頃
「金盞花」はキク科のキンセンカではなく、水仙の花のことです。
「金盞」は黄金の杯のことで、6枚の花弁の真ん中に、
黄色い杯のような副花冠をもつ、水仙の異名と言われています。
この時期に咲く水仙はお正月の花としても重宝されました。
この季節の食べ物
春菊
独特の香りがあり、鍋料理には欠かせない食材です。
おひたしや天ぷらにしても美味しくいただけます。
強い香りの成分であるリモネンは、
食欲増進や咳止めの効果があり古くから漢方として使われてきました。
カロテンやビタミンB2、カルシム、鉄分などが含まれています。
春菊は火を通しすぎると苦みが出てしまうので、鍋の時には10秒ほど入れるのがおすすめです。
白菜
冬の野菜の代名詞とも言える白菜です。
独特の甘さは霜にじっくりと当たることで作られます。
中国北部が原産で、11月から2月に旬を迎えます。
白菜は大部分が水分でできているため、ヘルシーな野菜です。
カロリーが低いのにも関わらず、ミネラルやビタミンK、
葉酸など栄養は豊富なので、白菜料理を召し上がる際には栄養が溶け出した汁も
一緒に頂くことをオススメします。
毛ガニ
北海道ではカニといえばこの毛ガニを指す場合が多いです。
東北以北の太平洋、日本海やオホーツク海で獲れます。
毛ガニは、カニの中ではやや身が小ぶりですが、
甘味のある足の身・濃厚な蟹味噌がとても人気です。
身や蟹味噌をいただいた後は、甲羅酒にするとさらに美味しくいただけます。
シャコ
シャコは見た目はエビに似ていますが、
ハサミを持ち十脚目に分類されるエビやカニとは異なり、
口脚目(シャコ目)に分類されます。
寿司ダネではさっと煮たものに甘辛いタレを塗って食します。
旬は3〜5月、10月〜12月の2回あります。
春の旬はめすの産卵期を控えて卵巣が発達し、
秋〜冬の旬は身がぎゅっと充実してオスメス共に美味しい時期です。
この季節の草花
竜脳菊(リュウノウギク)
10月から11月にかけて白い花を咲かせる野菊です。
福島県より西の日当たりの良い丘陵や山地に生えます。
竜脳のような香りがすることからこの名前が付けられました。
竜脳とは、マラヤ・スマトラ・ボルネオなどの
熱帯アジアに分布するフタバガキ科の常緑樹から取られた結晶で、
発汗・去痰・痛み止めの効果があることから薬や香料などに用いられます。
水仙
早いものは11月中旬に咲き始めます。
春までの間、白や黄色の花で人々の目を楽しませてくれます。
飾る時には1つの花に対して4枚以上の葉を組むと美しいです。
水仙はとても育てやすく数年間は植えっぱなしで管理でき、
環境が合えば球根が年々増えていくのでガーデニングでもとても人気が高い花です。
葉や球根には毒が含まれるため食用には適しません。
紫紺野牡丹(シコンノボタン)
ブラジル原産の熱帯花木です。
一般的に花が少なくなる秋から冬にかけて、
たくさんの花を咲かせることから庭木としても人気があります。
名前の通り深みのある濃い紫紺の花を咲かせ、上品な雰囲気を演出します。
一日花なので1つ1つの花はすぐに枯れてしまいますが、
夏から秋にかけての時期は次々と新しい花を咲かせ流ので長く楽しめます。
茶の花
椿の仲間の常緑樹です。
白色の5枚の小さな花びらの中に、ふわふわとした黄色い蕊(しべ)がとても可愛らしく、
茶花としても愛されてきました。
一見白椿のようにも見えるこの花は、
10月から11月頃にかけてうつむいたように下向きに咲きます。
茶の花は食べることができ、天ぷらにしたり、
煮詰めてお茶漬けの具にしたりする地域もあるそうです。
山茶花(サザンカ)
ツバキ科の常緑広葉樹です。
白・赤・ピンク色の花を咲かせ、10月頃から翌年の2月頃まで長く咲くものもあり、
とても良い香りがするのが特徴です。
見た目は椿ととてもよく似ておりますが、花の散り方は違います。
椿は花が丸ごとポトッと落ちるのに対し、
サザンカは花びらが1枚ずつばらけて地面に落ちます。
真冬にも花を咲かせることから、古くから寺院などの庭木に用いられてきました。
この季節の生き物
エゾシカ
日本には7種類のニホンジカが生息しており、
その中でも一番寒い北海道にのみに生息する鹿です。
ホンシュウジカのオスの体重が約90kgに対し、
エゾシカは約140kgあり、7種類のニホンジカの中で最も体が大きいです。
明治初期には乱獲や大雪などの影響により絶滅寸前まで激減しましたが、
その後の保護政策によりここ30年でエゾシカは急増しました。
現在は道内で60万頭以上が生息しています。
エゾシカが急増したことで、自動車や列車との交通事故が起こったり、
畑や植林の木、希少植物を食べてしまったり…と、
人間の暮らしにも影響が出ています。
マヒワ
体長約12.5cmの小さい鳥です。
鮮やかで美しい黄緑〜黄色をしており、
冬になると日本全国に飛来してくる渡り鳥です。
スギ、マツ類などの小さな種子を食べたり、
タンポポ、ヨモギ、マツヨイグサなどの種子などを食べます。
一羽で居ることは少なく、群れを作って飛び、
春先には木の枝に多く集まってさえずります。
見た目の美しさゆえに昔は愛玩用として飼育されていましたが、
現在は禁止されています。
この季節の行事やオススメ
出雲大社の神在祭(かみありさい)
11月3日 〜10日頃(旧暦10月10日〜17日)
旧暦の10月は全国の八百万の神々が出雲国に集まる月です。
他の土地の神様は留守になるので「神無月」と言いますが、
出雲の国では「神在月」と呼んでいます。
神々が集う出雲神社では「神迎祭」から始まり「神在祭」、
全国に神々を送る「神等去出祭(からさでさい)」が行われます。
神在祭の初日は出雲大社から近い稲佐の浜で神様を迎えます。
龍蛇神を先導に参拝者が続き、
いづも大社へと伸びる神迎えの道に長い行列ができます。
七五三
11月15日
男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳の時に行います。
これらの年齢は子どもの厄年と言われ、
社寺で厄落としをすると共にさらなる成長を願って晴着を着せて詣でる行事です。
昔は今ほど医療が整っていなかったため、
7歳まで無事に育つ確率はもっと低かったそうです。
七五三の縁起物である千歳飴(ちとせあめ)は、
その名前の通り長寿を願うものです。
江戸時代に浅草の飴売りの七兵衛が売り出したのが始まりとされています。
節分に歳と同じ数の豆を食べると良いのと同じで、
歳の数の千歳飴を袋に入れて子どもに持たせると縁起が良いとされています。
嵐山もみじ祭
11月の第二日曜日
京都嵯峨野の山が色づく頃に行われるお祭りです。
平安貴族がこよなく愛した嵐山や小倉山のもみじの美しさを讃え、
もみじに感謝するとともに、一帯を守る嵐山蔵王権現に感謝をする行事です。
渡月橋の上流の大堰川(おおいがわ)に数隻の船が浮かび、
平安時代の貴族装束に身を包んだ人々が船ごとに狂言や舞、
神楽演奏などを披露します。
伏見稲荷大社火焚祭
11月8日
稲荷神社の総本宮である伏見稲荷大社の神事です。
秋の収穫の後に、稲を育てた太一や太陽に感謝をする火祭です。
神前の稲藁に火を焚き、秋の実りに感謝するとともに
罪障消滅・万福招来を祈願します。
このお祭りは古くから伝わる重要神事の一つで、
本殿祭が終了した後には三基の火床が設けられ、
奉納された十数万本もの火焚串が次々と炊き上げられます。
本殿前庭では雅楽の調べに乗せた古雅な御神楽が行われるのも見所です。
ボジョレー・ヌーヴォー
11月の第三木曜日
毎年この日に解禁されるフランス・パリのボジョレー地方のワインのことです。
その年に収穫された黒ブドウから作られるため、
急速に発酵させる特殊な技術を使って作られます。
そのため、わずかに炭酸が含まれ清涼感があるワインです。
ボジョレー・ヌーヴォーが世界で注目を集め始めた頃、
ワインの売り手たちはいち早く出荷しようと競い始めました。
その結果質の悪いワインも多く出回ってしまいました。
そこで1967年にフランス政府はワインの品質を下げないために解禁日を定めました。
日付変更線の関係上、日本では本国フランスよりも早い解禁日を迎え、
毎年解禁日にはニュースでも大きく取り上げられます。
written by はれる88