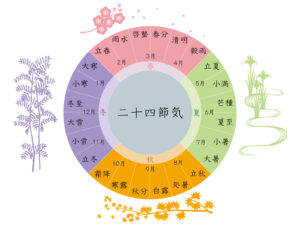雨水(うすい)

雨水(うすい):2月18〜3月4日頃
降っていたものが雪から雨へと変わり、雪や氷は溶けて水になり、土が潤う時期。
恵の雨が土を潤し、春の草花が育ちます。
この頃は目にする風景や体感する温度・日差しがはっきりと変わるので、
春の訪れを実感しやすいです。また、昔から雨水は農作業を始める時期の目安となっていました。
この頃の雨は雪を溶かす「雪消しの雨」甘の心地よさを意味する「甘雨」、
また「養花雨」や「慈雨」と呼ばれており、
名前の通り今までの乾いた土壌を潤し草木を養い慈しむ雨とされています。
⑴土脈潤起(つちのしょううるおいおこる)
2月19日~23日頃
雪が雨に変わり、足元の凍った土は少しずつ湿り溶け、水蒸気が低く漂う情景。
大地の柔らかな温もりは春の訪れを感じさせます。土に植物が芽吹くための潤いをもたらします。
ふきのとうが顔を出すと、人々はいよいよ春が訪れたことを感じます。
春が近づき初めて吹く暖かい南風の強風、春一番が吹くのもこの頃です。
⑵霞始靆(かすみはじめてたなびく)
2月24日~28日頃
雨や雪解け水の影響で湿度が高くなり、また気温も少しずつ上がるため霞が発生する頻度が増えます。
発生した水蒸気が山野にたちこめ、山々がぼんやりとかすんで山の姿を隠します。
特に、あたり一面に広がる霞が陽の光を集め、ほんのりピンク〜薄紫色に見える朝焼けや夕焼けは、
昔から多くの人々の心を打ちました。
「春は霞・秋は霧」といって万葉集に出てくる多くの歌にも読まれる程、
いかにも春めいた幻想的な風景が見られるようになります。
⑶草木萌動(そうもくきざしうごく)
3月1日~5日頃
「下萌」や「草萌」とも呼ばれる芽吹きの瞬間を表しています。
うららかな日差しに誘われていつのまにか草木の若葉が芽生え、冬枯れの風景にも春の兆しが見えます。
暖かい陽の光が差し、草木の若芽は次第に黄緑色の色味を深め、本格的な春へと移ろっていきます。
この季節の食べ物
ハマグリ
元々の組み合わせでしかぴったりと合わないハマグリは、昔からその特性を生かして様々に活用されてきました。
平安時代には貴族の間で「貝合わせ」という神経衰弱のような遊びもされていました。
90個以上の貝殻を並べ、一つの貝殻に合うものを探したり、その会を題材にした歌を詠んだりして遊んでいました。
また、元々のペアでしか合わせられないことから、良縁や夫婦円満の象徴としても扱われてきました。
ひな祭りにハマグリのお吸い物をいただくのはそういった意味があります。
ワカメ
縄文時代の遺跡で発見され、万葉集にも詠われ、古くから日本人に愛されてきた海藻の一つです。
ワカメは低カロリーでミネラルが豊富なので美容や健康にとても良い食材です。
年中食卓に並ぶワカメですが、旬は3月〜5月でその頃が最盛期となります。
デコポン
清美とポンカンを交配させた柑橘類です。元々の名前は「不知火(しらぬい)」といい、
上部(デコ)がポンと飛び出していてる見た目が特徴です。
不知火の中でも基準をクリアし農協から出荷されたものが「デコポン」と呼ばれます。
酸味が少なく甘みがあります。
いかなご
日本各地に生息するスズキ系イカナゴ属の魚です。毎年2月下旬から漁が解禁となります。
いかなごは関西では体長2cmくらいのものを「新子(しんこ)」、
25cm前後の成魚になると「古背(ふるせ)」と呼ばれます。
阪神・播磨・淡路地域の郷土料理の「いかなごのくぎ煮」は有名で今では多くの地域でも愛されています。
菜の花
明るい色で元気がいっぱいの菜の花。油菜、花菜は略して「菜」と世慣れ、その花が「菜の花」です。
少し苦味がありますが栄養素が豊富で、和え物や炒め物などで多く食されています。
ふきのとう
雪解けした地面から顔をだすフキノトウ。
花が咲く前の柔らかいうちにいただくのが特に美味しいです。
天ぷらにすると美味しく、ほろ苦さと清涼感があり、
冬の寒さでのんびりしていた身体を目覚めさせてくれるような春の味です。
この季節の草花
オオイヌノフグリ
オオバコ科クワガタソウ属の植物です。明治初期に帰化したとされています。
コバルトブルーの小さな花があたり一面に広がり、春を感じさせます。
花は蜜を含み、ことりや虫が集まる姿がよく見られます。
日が昇ると咲き、夕方にはしぼみ、翌日また咲いて3日ほど咲き続けます。
ネコヤナギ
日本全国に分布し、特に小川の辺りや湿地などでよく見られます。
ヤナギ科の落葉低木で、分岐しない長い枝にいくつもの銀白色のふわふわとした花穂をつけます。
まるで猫のシッポのような柔らかさで「ネコヤナギ」の名前がつきました。
はこべ
春の七草の一つです。地面を這うように成長するのでうっかり見落としてしまいがちですが、
道端・あぜ道・花壇のすみなど、いたるところに咲いています。
全国に分布しており、白く小さな花は陽の光を浴びると星型に開き、天気が悪い日は閉じています。
椿
千利休が好きだったという花です。咲く時期も長く多くの種類がありますが、
日本人の心を惹きつける品があります。
椿油は種子を砕いて蒸し、絞ったもので食用にしたり、髪の潤いなどに効果があります。
馬酔木(あせび)
白や淡いピンクが鈴なりに咲く様子がとても可愛らしい植物です。
葉や茎に有毒のアセトポキシンが服荒れていることから、
昔は葉の粉末や汁を害虫よけとして使っていました。
これを馬が誤って久池井にするとふらつくことから「馬酔木」と名付けられました。
万葉集などでも春の季語として使われています。
木瓜(ぼけ)
バラ科ボケ属の落葉低木です。3月〜5月に赤・白・ピンク・オレンジの花を咲かせます。
丸みを帯びた花弁で華やかな花です。
元々は「モケ」「モッケ」「ボックワ」と呼ばれていましたが、
その後に実が瓜に似ていることで「木瓜(ボケ)」と呼ばれるようになりました。
9月〜10月に香りが良い青い実をつけ、果実酒やジャムとして親しまれています。
この季節の生き物
雲雀(ヒバリ)
スズメ目ヒバリ科に分類される鳥で、体長は17cmほどあります。
積雪のある地域では冬場に南下することから、
北海道などの寒い地域では春から夏にかけてやってくる「夏鳥」として知られています。
ヒバリは様々な声で鳴くことで有名で、地面から飛び立つ時に「ピュルピュル」と鳴いたり、
繁殖期にオスがメスにアピールする時に鳴いたりします。
これらは「高鳴き」と呼ばれ、長い時には20分近く鳴くこともあるようです。
魴鮄(ホウボウ)
昔から祝い魚として有名です。
江戸時代から上流階級の食べるものになっていました。
鮮やかで大きな胸ビレを持っているのが特徴です。
ホウボウは頭が固く「頭の骨が固くなるように」という意味や、
鳴き声を出すことから「夜泣きしませんように」と
願いをこめてお食い初めの魚として親しまれてきました。
越年トンボ(オツネントンボ)
アオイトトンボ科の昆虫です。
昆虫は通常卵や蛹の姿で冬の寒さを乗り切りますが、オツネントンボは異なります。
成虫で冬を越すのでとても珍しく、トンボの仲間で越冬するものはこれを含めたわずか数種類のみです。
この季節の行事やオススメ
寒天干し
12月半ば〜2月半ば頃まで
信州諏訪地方では寒さが最も厳しいこの時期にだけ見ることができる寒天干しが有名です。
ところてんを竹に乗せ、10日〜2週間ほど乾燥させます、片側が乾燥したら裏返し、雨の日はシートをかぶせます。
この工程を繰り返し4センチ角、長さ30cmほどの角寒天を作ります。
太子会・春会式
2月22日
聖徳太子の命日である2月22日に京都広隆寺などで聖徳太子を偲ぶ法会「太子会」が営まれます。
また兵庫県太子町の斑鳩寺では「春会式」が開かれます。
露店や植木市が開かれ、たくさんの参拝客が訪れます。
河津桜祭り
2月〜3月上旬
早咲きの桜として有名な名所のお祭りです。
河津桜の原木は1955年に静岡県賀茂郡河津町で発見されました。
そこから大切に増やされて、河津駅近くの河口から3キロほど続く河津桜並木は毎年大勢の人で賑わいます。
修二会(しゅにえ)
3月1日〜14日頃
毎年お正月に「修正会(しゅうしょうえ)」といって、
罪や穢れを仏に懺悔し五穀豊穣などを祈願する仏教法会があります。
同じく毎年旧暦の2月に行われる懺過の法会が「修二会」です。
特に奈良県の東大寺二月堂で行われる修二会が有名で、3月1日〜14日の間に様々な行事が行われます。
3月13日未明からは主要行事であるお水取りが始まります。
本堂の十一面観音に備えた「お香水」と呼ばれる水を飲むことで病気が治癒すると伝えられてきました。
かつてはお水取りの行事が旧暦の2月1日に行われてきたことから、春迎えの行事となっています。
桃の節句
3月3日
桃の咲く季節の節句「桃の節句」は、
・1月7日「人日(じんじつ)」
・3月3日「上巳(じょうし)」
・5月5日「端午」
・7月7日「七夕」
・9月9日「重陽(ちょうよう)」
と、合わせて五節句に数えられます。
陰陽思想では奇数がおめでたい数字とされてきました。
そのため人日の節句を除いて、いずれの節句も同じ奇数が重なる日となっており、
1年のうちでも二十四節気よりさらい大きな節目とされてきました。
かつてはあ「穢れ・不浄」を忌み嫌い、「ハレ・清浄」を尊ぶ信仰がありました。
旧暦の3月は農耕を始める直前にあたり、上巳の節句は禊(みそぎ)の意味がありました。
古代中国ではこの日に、水辺で草花を体に塗って穢れを祓い身を清める風習がありました。
これが日本に伝わり、上巳の日の紙で作った人形で体をなでて身の穢れをうつし、
厄災を人形に渡して流す「流し雛」へとなりました。
これに加わり平安時代公家の女の子たちの間で広まった雛遊びという人形遊びが結びついて
雛飾りへと変化したと言われています。
そして江戸時代になり、現代のように雛人形を飾り女の子の成長を願うという風習が定着しました。
writtn by はれる88