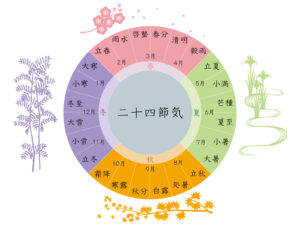芒種(ぼうしゅ)

芒種(ぼうしゅ):6月5日頃
芒(のぎ)のある穀物の種蒔きをする頃です。
芒とは、イネ科の植物の先端にある針のような突起のことを示します。
現代の田植えはもっと早い時期に行いますが昔はこの頃でした。
諸説ありますが、稲の語源は「命の根」だという説もあります。
また、立春から127日目で芒種の中旬に当たる6月11日頃からは暦の上では入梅(梅雨入り)となります。
一足早い入梅の沖縄では「小満芒種」という梅雨の別名があります。
⑴蟷螂生(かまきりしょうず)
6月6日~10日頃
秋のうちに葉の裏や外壁などに産み付けられたカマキリの卵が孵化します。
カマキリの卵は200〜300個の小さな卵の集合体です。
その卵から一斉にカマキリがかえります。
カマキリは生まれた頃から親と同じ姿をしており、
前足には小さいながらしっかりと形のある鎌があります。
作物には手をつけずに害虫を捕まえる益虫としても知られています。
ことわざ「蟷螂(とうろう)の斧」はカマキリが前足をあげて、
大きな車の進行を制御しようとする姿から弱小のものが自分の力量をわきまえず強敵に向かう、
儚い抵抗のたとえとされます。
⑵腐草為螢(ふそうほたるとなる)
6月11日~15日頃
梅雨が始まる頃、高温多湿でじっとりとした空気が漂う中、腐りかけた草の下から蛍が出てきます。
昔は腐った草が化けて蛍に生まれ変わると考えられていたそうです。
蛍は「朽草(くちくさ)」という別名を持っており、
蛍の生態系などが解明されていなかった昔ならではの風情豊かな発想が伺えます。
⑶梅子黄(うめのみきなり)
6月16日~20日頃
梅雨の到来とともに、青々と大きく実った梅は黄色く色づき始めます。
梅の実は生食には向かないため、梅干しや梅酒として食されてきました。
「梅雨」という名前はちょうど梅が色づく頃に降る雨であることに由来します。
この季節の食べ物
鮎(あゆ)
キュウリに似た独特の香りをもつことから「香魚」とも呼ばれています。
鮎の由来は神功皇后がかつて鮎を釣って戦いの勝敗を占ったことから、
魚篇に「占」という字が書かれるようになったそうです。
清流で育った鮎は腹わたもほろ苦くて美味しくいただけます。
塩焼きはタデ科の植物をすりつぶして酢でのばした「タデ酢」でいただくのが定番です。
トウモロコシ
夏のイメージが強いトウモロコシですが、全国的な旬は6月から9月の中旬頃です。
糖やでんぷんなどの炭水化物が多く、野菜の中ではエネルギーが高い食材です。
またノール酸が豊富に含まれているため、コレステロール値を下げる作用があります。
腸をキレイにするセルロースも含まれているので身体に良いとされています。
オクラ
6月〜8月ごろが旬の野菜です。
オクラはアオイ科の植物で、ハイビスカスの仲間に分類されます。
そのため、暑さや真夏の直射日光、降り注ぐ雨にも強く、
この頃から始まる高温多湿な気候でも元気に育ちます。
ネバネバ成分のペクチンとムチンには食物繊維がたっぷり含まれており、
整腸作用があり、免疫力を高めてくれる効果があります。
断面の星型を生かして料理のトッピングとしても目を楽しませてくれます。
クセのない食べやすい味なので子供にも好まれやすいです。
アナゴ
ウナギ目アナゴ科に属する魚類の総称です。
ウナギに似た細長い体型をしており、天ぷら・寿司ダネ・焼きアナゴなど様々な方法で食されてきました。
年間を通して多く流通しているアナゴですが、
6月から8月にかけては「梅雨穴子」「夏穴子」と呼ばれ、脂が少なく淡白であっさりとした味わいが特徴です。
ホヤ
海のパイナップルと呼ばれ、デコボコとしたオレンジ色の独特な見た目をしている海の生物です。
ホヤの旬は5月から8月と言われており、その水揚げ量は宮城県が一番多いです。
新鮮なホヤは刺身で食べることができ、酢の物や天ぷら、素焼きもおすすめです。
新生姜
1年中手に入る「ひねショウガ」と比べて、初夏に出回る新生姜は色が白く、香りも良く、
またみずみずしく、柔らかいです。1年の中でこの時期にしか手に入りません。
薄くスライスして甘酢漬けにして食べるのが一般的です。
この季節の草花
ナツツバキ
ナツツバキは古くから寺院などの庭に「シャラノキ」として植えられてきました。
椿という名前ですが6月、梅雨ごろに花が咲きます。
紫陽花(あじさい)
咲き初めは白っぽく、梅雨に入る6月から7月頃にかけて雨に似合うピンク~青の細かい花を咲かせます。
土壌がアルカリ性なら赤っぽく、また酸性であれば青っぽく花が色づくと言われています。
紫陽花は藍色のものが集まったもの「集真藍(あづさい)」が語源とされています。
様々な色の違いを楽しめる紫陽花には「移り気」という花言葉があります。
神奈川県鎌倉市の明月院、千葉県松戸市の本土寺、千葉県大多喜町の麻綿原天拝園などが花の名所として知られています。
桔梗(ききょう)
東アジアに分布する多年草です。
開花時期は6月〜8月上旬です。
秋の七草の一つに数えられるため、秋をイメージする人が多いですが夏の花です。
古来から美しい花が人々に愛され万葉の時代から鑑賞されていました。
その美しい形から家紋に取り入れられることもありました。
また江戸城には「ききょうの間」や「桔梗門」があります。
「清楚、気品」という花言葉があります。
ツユクサ
北海道から沖縄まで全国各地に分布しており6月〜10月に咲く一年草の花です。
朝露を受けて咲き始め、午後になるとしぼみます。
二つに折れになった苞(ほう)の間から青色の花が次々と咲きます。
深みのある青い花びらから黄色い雄しべが鮮やかに顔を出している様子はなんとも可愛らしいです。
また、花びらからは染料に使える青色の水が取れます。
この季節の生き物
カタツムリ
梅雨の時期、紫陽花と雨に加えて思い出されるのはカタツムリです。
カタツムリは乾燥と寒さが苦手なので高温多湿な梅雨の時期になると出てきます。
乾燥すると、ネバネバした液体で体を保護し、乾燥がひどい時には殻に閉じこもります。
日本には約800種以上が生息しており、行動範囲が狭いため地域ごとに分化し、多くの種類に分かれています。
蛍(ほたる)
日本には約40種類の蛍がいます。
しかしお尻の辺りが光るのはゲンジボタルやヘイケボタルと呼ばれる数種類のみです。
これらの蛍は、一生のほとんどを幼虫の姿で土の中で過ごします。
土の中で蛹になり、成虫になると口が退化して水しか摂取できなくなってしまいます。
そのため蛍は成虫になってから1週間ほどしか生き延びられません。
アオバズク
フクロウの仲間で、全長約30cmほどの鳥です。
黄色い目をしておりオスよりもメスの方が体が大きいです。
頭から上面、翼の上面、尾は黒褐色をしており、
お腹の部分は白色で黒褐色の太い点が繋がった縦班があります。
「ホッホウ、ホッホウ」とふた声ずつ繰り返しさえずります。
青葉が茂り出す頃に飛来するので「アオバズク」という名前がついたと言われています。
低地から山林の林におり、大木に巣として使える洞があればお寺や神社の敷地内でも繁殖します。
この季節の行事やオススメ
時の記念日
6月10日
腕時計や懐中時計が普及しておらず、
人々が時間をあまり気にすることなくのんびり暮らしていた時代に、
国民にきちんと時間を守らせようとして制定された記念日です。
1920年(大正9年)に生活改善同盟会によって制定されました。
日本書紀には、天智天皇の御世である671年4月25日(太陽暦の6月10日)の項に
「漏尅(水時計)を新台に起き、始めて候時を打つ」とあります。
この日は日本で初めて時計が時を告げたことに由来しています。
葛飾菖蒲祭り
5月末~6月中旬
東京都葛飾区の堀切菖蒲園と水元公園で開催される祭りです。
堀切菖蒲園の花菖蒲は江戸名所の一つとして古くから知られており、
その景観の美しさから安藤広重や歌川豊国らの錦絵の題材にもなりました。
約100種、1万4000株の花菖蒲は圧巻です。
期間中の土日はパレードやライトアップなどが行われ多くの観光客で賑わいます。
鮎の友釣り
鮎釣りにも色々な手法があり、
鮎の友釣りと呼ばれるのは鮎の縄張りの習性を利用した日本独特の釣法です。
オトリとなる鮎を使い、流れに放し、
縄張りを守ろうとオトリアユに体当たりしてくる鮎をつる方法です。
流れの速い渓流でよく使われます。
川ごとにアユ釣り解禁日が設けられ、その日になると多くの釣り人が集まります。
箱根登山鉄道の紫陽花
6月中旬
紫陽花の咲く時期の箱根登山電車は「あじさい電車」と呼ばれています。
箱根湯本駅からケーブルカー沿線まで、山の標高差によって紫陽花の開花時期も移ろっていきます。
線路の両側に広がるあたり一面の紫陽花と電車の赤い車体のコントラストがとても美しく、
またゆっくり走る登山電車の車窓からの紫陽花の眺めはとても幻想的です。
入梅
6月11日
夏の手前の雨季を表す言葉です。
黄経(太陽の経路)が80度になる新暦6月11日ごろに当たります。
旧暦では、新暦の6月6日ごろに当たる芒種の後にある壬(みずのえ)の日でした。
旧暦の梅雨入りの方が実際の梅雨入りに近いようです。
梅雨といえば細い雨が毎日降り続き、湿度も高くジメジメとした過ごしにくい時期です。
大陸の冷たい高気圧と太平洋の暖かい高気圧がぶつかり、
その間に梅雨前線が生まれることによって起こります。
入梅は6月11日ですが、日本列島は北南に伸びているため、実際の梅雨入りは各地で1ヶ月くらいの差が生まれます。
父の日
6月第三日曜日
父の日は母の日と同様アメリカで生まれた記念日です。
1910年、母に先立たれた父に育てられたジョン・ブルース・ドット夫人が、
母の日があるのに父の日を提唱したと言われています。
母の日には赤いカーネーションが一般的ですが、
父の日にはバラやユリを贈るとされています。
日本では父の日には花を贈るよりも、ネクタイやベルト・お酒などの実用的なものを贈る場合が多いです。
written by はれる88