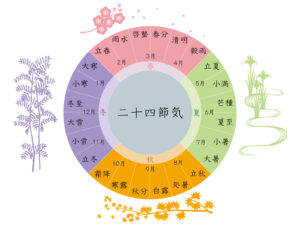秋分(しゅうぶん)

秋分(しゅうぶん):9月23日頃
春分と同じく、太陽が真東から昇って真西に沈む日です。
昼夜の日の長さはほぼ同じになりますが、「暑さ寒さも彼岸まで」という様に、
この頃から夜の長さが長くなります。
肌寒さとともに「秋の夜長」が実感されるようになります。
また彼岸では先祖供養を行い、稲刈りに向けては豊作を祝い、
無事に稲刈りをできた頃には感謝を捧げる時期でもあります。
⑴雷乃収声(らいすなわちこえをおさむ)
9月23日~27日頃
夕立に伴う雷がならなくなる頃。
夏の代名詞と言われ雷を呼ぶ入道雲から、
秋の代名詞であるうろこ雲へと、秋の空が晴れ渡ります。
一日ごとに涼しくなっていき、ここから本格的な秋へと季節が移ろってきます。
また梨やぶどうなどの秋の味覚が美味しくなる頃です。
⑵蟄虫坏戸(ちゅっちゅうこをはいす)
9月28日~10月2日頃
あたりの空気が涼しくなり始め冬の気配を感じ始める虫たちが、
まるで戸を塞ぐようにして姿を隠し始める頃です。
啓蟄の「蟄虫啓戸」と対になる時候です。
木の根元へ潜ったり、土の中で冬眠の準備を始めたり、
枯葉の中に潜んだり…とそれぞれが冬の巣ごもりの準備を始めます。
⑶水始涸(みずはじめてかれる)
10月3日~7日頃
田んぼから水を抜いて、十分に乾かしてから稲刈りに取り掛かる頃です。
稲刈り前の水を抜く作業を「落し水」、
稲を刈り取って切り株だけになったものを「刈田」と言います。
刈り取った稲が稲木にかけられている風景は、素朴で美しく、秋ならではの美しさがあります。
この季節の食べ物
秋鮭
9月から12月頃、産卵のために海から川へと戻る途中に獲れるシロサケのことを言います。
秋鮭は癖が少なくシチューやフライ、ムニエルなどに適しています。
鮭は獲れる時期や場所によって呼ばれる名前が異なります。
4月から7月頃に獲れる脂乗りが良い鮭を「時不知(ときしらず)」と言い、
ロシアの川に戻る途中に北海道円買いんで獲れるものを「鮭児(けいじ)」、
本州の河川に戻る途中の鮭が北海道沿岸で獲れたものを「目近(めぢか)」と言います。
秋鯖(あきさば)
家庭の食卓にもよく登場する鯖ですが、産卵を終えて、
冬に備えて多くのえさを食べている9月から11月に獲れる鯖は特に丸々と太り、
脂がたくさんのっています。
「鯖の生き腐れ」ということわざがある通り、
痛みやすく生臭みの元になる成分も多いので、
調理の際には酒や味噌、ショウガなどを使って臭みを取ると美味しくいただけます。
ゆず
爽やかな香りで、酒や香辛料などに使われる柑橘類です。
奈良時代から栽培されており、10〜11月頃に旬を迎えます。
ゆずの強い香りが邪気を払うとされていることから、
冬至には柚子風呂に入ります。
ハゼ
全長20cmほどの尖った背びれを持つ魚です。
素早く水中の中を馳ける魚であることから「馳せ(はせ)」が
ハゼになったと言われています。
透明感のある白身で、クセが少なく、皮にも風味があります。
天ぷらや煮物で食べるのが一般的です。
里芋
8月から10月頃に穫れる里芋は、
稲作が始まる前の縄文時代から栽培されており、
米以前より主食となっていました。
十五夜を別名「芋名月」ということもありますが、
これは里芋の収穫を祝って感謝するためこの様な名前がつきました。
里芋は食物繊維を多く含み、便秘解消にも役立ちます。
マガレイ
体長50cmほどの平らな魚です。
楕円形をした体の裏側には、黄色の線が2本あります。
年間を通してよく入荷があるので安価で手に入ります。
素焼きや煮物、ムニエルにすると美味しくいただけます。
ぶどう
ぶどうやマスカットの主な旬は7月から9月頃です。
ぶどうには多くの品種があり、それによって旬が異なりますが
「デラウェア」などの小粒は7〜8月、
「ピオーネ」や「巨峰」などの大粒は9月頃に旬を迎えます。
生で食べる他に、ジャム・ワイン・ジュースにしても美味しいです。
日本には奈良時代に伝わったとされています。
おはぎ
秋の彼岸には、もち米やうるち米などを丸めて粒あんなどで包んだおはぎをお供えします。
古くから、あずきの赤色には災難が降りかからない様にする効果があると言われており、
邪気を払う食べ物という意味合いから、先祖供養に用いられてきました。
名前の由来は諸説ありますが、
秋の七草の一つである萩の花とあずきの形状が似ているため、
「おはぎもち」と呼ばれていたのが「おはぎ」になったと言われています。
粒あんの他に、ゴマやきな粉で包むこともあります。
この季節の草花
葛(くず)
ツル植物で、繁殖力が強く、
ツルの長さは約20メートルにもなります。
和菓子「葛餅」「葛切り」や、根を原料とする漢方「葛根湯」など
なじみの深い植物でもあります。
萩・尾花(ススキ)・なでしこ・おみなえし・ふじばかま・桔梗と
並ぶ秋の七草にも指定されています。
秋の七草は春の七草の様に食べるものではなく、
愛でるものとされています。
奈良時代の歌人である山上憶良に
『秋の野に 咲きたる花を 指折り かき数ふれば 七種の花』
『萩の花 尾花葛花 なでしこの花 女郎花 また藤袴 朝顔の花』
と、詠まれて選定されました。
銀杏(イチョウ)
秋になると葉が黄色く色づく姿が美しい、
日本人になじみの深い植物です。
平安末期に中国から伝わったとされています。
名前の由来は中国語で「鴨脚(Yajiao)」からきているとされ、
イチョウの葉の形が鴨足に似ていることから付けられました。
種子が銀杏で独特の匂いを発しますが、加熱して食べるととても美味しいです。
東京の明治神宮外苑や大阪の御堂筋の並木道が名所として知られています。
金木犀
小さな橙色の花が集まって咲きます。
甘い香りが特徴で、秋風とともに金木犀の薫りがふんわりとすると
秋の深まりを感じます。
江戸時代に中国から伝わったとされています。
花びらを白ワインなどの酒に漬けて、
熟成させたものを桂花陳酒(けいかちんしゅ)といい、
楊貴妃がよく飲んでいたとされています。
リンドウ
本州から九州・四国まで広く分布し山野に自生して、
秋になると青紫色をした鐘状の花を上向きにして咲かせます。
リンドウは世界に1100種類以上の種があり、
その中のトウリンドウは根や茎根が漢方として使われます。
食欲不振や胃酸過多症、腹痛に用いられます。
この季節の生き物
赤とんぼ
アキアカネ・ナツアカネ・ノシメトンボなど
体の色が赤いトンボの総称です。
秋に平野や丘陵地帯でよく見られ、秋を告げる虫としても有名です。
体の色が特に赤いのはオス、メスは黄褐色をしていることが多いです。
トンボは古来、「あきつ」「あきづ」とも呼ばれていました。
秋の季語として古くから万葉集でも多く詠まれています。
キツツキ
くちばしで樹木の幹をつついて穴を開け、
中にいる昆虫を長い舌を使って食べます。「
木突き」が名前の由来となりました。
日本にはコゲラ、アオゲラなど10種類が分布しています。
彼岸花
ヒガンバナ科の多年草で、
秋の彼岸の頃に花を咲かせるのが名前の由来となっています。
1日に10cmほど伸び、50cmくらいの高さまで成長します。
天に向かって咲く赤い花という意味で「曼珠沙華(マンジュシャゲ)」と
呼ばれることもあります。
また、虫除けのために墓地に植えられることも多く、
このことが「死」を連想させるため「死人花(しびとばな)」「幽霊花」とも
呼ばれることもあります。
強い毒があり、誤って食べると嘔気が出ることもあるので要注意です。
もず
全長は20cmほどの鳥で、「百舌(モズ)」とも言うように、
他の鳥の鳴き声がとても上手です。
またモズは生垣などの尖った小枝や有刺鉄線の棘などに昆虫やバッタ、
カエルなどを串刺しにする習性があります。
これを「モズのはやにえ」と言います。
鋭いくちばしで昆虫だけでなく魚も獲物にしてしまいます
この季節の行事やオススメ
秋のお彼岸
9月20日頃〜9月26日頃
秋分を中日として前後3日の計7日が秋のお彼岸です。
春のお彼岸には「自然をたたえ、生物をいつくしむ」という目的があったのに対し、
秋のお彼岸は「先祖をうやまい、亡くなった人々をしのぶ」という目的があります。
よって、秋のお彼岸には先祖の墓参りや法要を行うことが多いです。
また春のお彼岸ではぼた餅をお供えするのに対し、
秋のお彼岸には邪気を払うとされる小豆を使ったおはぎをお供えします。
うろこ雲
秋の空によく見られる雲で、魚のうろこ状に広がります。
高度5000〜1万5000キロの高い空にできる「巻積雲」の総称で、
小さな雲がたくさん集まって見えます。
他に「鯖雲(さばぐも)」「鰯雲(いわしぐも)」などの種類があります。
うろこ雲と似たもので「羊雲」もありますが、
こちらは高度2000キロから7000キロほどにできる「高積雲」で、
巻積雲よりも大きな雲がたくさん集まったものです。
いずれも秋の季語ですが、
手を伸ばして一つの雲の塊が小指の爪ほどの大きさであれば「巻積雲」、
人差し指ほどの大きさであれば「高積雲」だと見分けることができます。
衣替え
10月1日
夏服への衣替えは6月1日、冬服への衣替えは10月1日に行うのが一般的ですが、
江戸時代は年に4回の衣替えが行われていました。
その年の気候によって時期をずらして行う場合もありますが、
最低気温が18℃をきった乾燥した日に行うのがおすすめです。
秋雨前線
9月中旬から10月中旬
夏から秋に移り変わる頃、真夏の猛暑をもたらす高気圧が南へ退き、
北からは大気の冷たい高気圧が張り出します。
これらの異なる性質の高気圧がぶつかり合うことで、
大気の状態が不安定になり、日本列島には秋の長雨の原因となる秋雨前線が停滞します。
梅雨前線と比べて停滞する期間は短いですが、
台風の影響と重なると大雨になることがあります。
花馬祭(はなうままつり)
10月初旬
長野県や岐阜県で重要無形民俗文化財に指定されているお祭りです。
800年以上も前から続くお祭りで、木曽義仲の出世を祝い、
馬を引いて村人総出で歌って踊ったのが始まりとされています。
今では五穀豊穣を祈願する催しとなりました。
花櫛と呼ばれる色紙で飾られた竹串を背負った三頭の木曽馬が、
笛や太鼓とともに神社へと練り歩きます。
written by はれる88