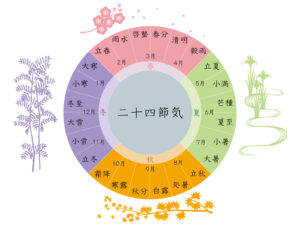寒露(かんろ)

寒露(かんろ):10月8日頃
露が冷たく感じられる季節です。
露が凍りかけて霜になろうとすることを「寒露」と言います。
野山の色彩は濃くなり、朝晩は寒さを感じるようになります。
「秋の日はつるべ落とし」とことわざで言うように、
夕日が沈むまでの時間がとても短い時季が始まります。
真っ赤な夕日に染まるに哀愁を感じるのは日本人特有の完成かも知れませんね。
この頃になると北国では初氷、
標高の高い山では初冠雪のニュースが聞かれ、
空気が澄むことで夜空には美しい月が輝く季節です。
⑴鴻雁来(こうがんきたる)
10月8日~12日頃
雁がシベリアやカムチャッカから渡ってくる頃です。
雁の他の代表的な渡り鳥はカモやツグミ、
電車の名前にもなっているユリカモメです。
その年に初めて訪れる雁を「初雁(はつかり)」と呼びます。
またこの頃に吹く北風のことを「雁渡し(かりわたし)」と言います。
昔の人は空を見上げながらこの風を感じ、秋の潮を予感していたのかもしれません。
⑵菊花開(きくはなひらく)
10月13日~17日頃
菊の花が咲き始める頃です。
各地で菊の品評会や菊祭りが開かれ賑わいます。
学問の神様で知られる菅原道真が16歳の時に詠んだ「残菊」にちなんで、
湯島天神をはじめとする全国の天満宮ではこの時期に菊祭りが開催されます。
福岡県の太宰府天満宮では、
晩秋の菊を愛でる伝統行事「残菊の宴」が秋の風物詩となっています。
残菊の宴は964年に始まったと言われ、大変歴史が長い行事です。
⑶蟋蟀在戸(しっそくこにあり)
10月18日~22日頃
「蟋蟀」とはキリギリスまたはコオロギのことです。
(どちらが正しいかは諸説ありますが、ここではツヅレサセコオロギを指すのでは、とも言われています。)
ふと気付くと、キリギリスやコオロギが戸口で鳴いている様子を表します。
この季節の食べ物
栗
9〜10月に旬を迎える栗ですが、
日本で多く出回っているのはニホングリと呼ばれるものです。
一般的に栗は大きく分けて3種類ありニホングリの他に、
焼き栗で有名な天津甘栗(チュウゴクグリ)、マロングラッセで有名なヨーロッパグリがあります。
日本で栽培されているニホングリは、野生のシバグリから品種改良されたものです。
栗は脂肪分が少なく、ヘルシーな果物です。
ビタミンやカリウムなども含まれ、食物繊維も多いので便秘解消にも効果があります。
ハタハタ
スズキ目の魚で北海道太平洋岸やオホーツク海沿岸などに生息しています。
秋田県や山形県の郷土料理には欠かせない魚で、
鱗がないため皮は破れやすく、骨まで柔らかく、塩焼きや酢じめ、田楽などで食べられています。
秋田の郷土料理「しょっつる鍋」で使うしょっつるはハタハタを塩漬けにして、
樽の中で発酵・成熟させて造られる醤油のことです。
とても歴史がある醤油なので、石川県の「いしる」、
香川県の「いかなご醤油」と並んで日本三大醤油と呼ばれています。
りんご
人類が食した最古の果物と言われており、
起源は約8000年前とされています。
栄養価が高く食べやすいため、
子供からお年寄りまで幅広い層に世界中から好まれています。
生食だけでなく焼き菓子やジャム、ジュースにしても美味しくいただけます。
リンゴにはリンゴ酸やクエン酸など、
有機酸が豊富に含まれているため疲労回復効果があります。
また、ペクチンによる整腸作用・コレステロールの吸収抑制作用も期待できます。
日本の生産量で一番多いものは「ふじ」で、
甘みと酸味のバランスが良く、長く愛されています。
ボラ
秋に旬を迎える出世魚です。
3cm前後:ハク
10cmまで:スバシリ
5〜18cm:オボコ
10〜25cm:イナ
30〜40cm:ボラ
40cm〜:トド
と、体の大きさによって呼び方が変わります。
日本では関東以南で多く獲れます。
ボラは刺身、焼き、煮付けなどの調理をすることが多いですが、
白子や卵巣も市場に出回り高値で取引されます。
特にボラの卵巣を塩干しした「からすみ」は特に人気が高い珍味とされています。
この季節の草花
菊
1868年に皇室の紋章に定められた日本のシンボルの花とも言えます。
「高貴」「高尚」という花言葉があり、古来から大切にされてきた花です。
新暦9月9日の重陽の節句は、別名菊の節句とも呼ばれ、菊を飾ったり、
菊酒を楽しむ風習がありますが、その頃にはまだ自然の菊の花は咲きません。
旧暦の9月9日頃(新暦の10月初旬〜中旬)になると菊は綺麗に花を咲かせます。
また、旧暦の重陽の節句の日に積んだ花びらを乾かして詰め物にして作る枕を「菊枕」と言います。
頭痛や目に効能があると言われる他、菊の香り漂う寝心地に、
好きな人が夢に現れるとも言われ、女性から男性へ贈られていたそうです。
フヨウ
アオイ科の植物で、ピンク色が可愛らしい大輪の花を咲かせます。
朝に咲いた花が色を変化させながら夕方になるとしぼんでしまう一日花です。
中国から渡ってきたと推測されており、日本での歴史も古く、
室町時代には鑑賞されていた記録があります。
園芸品種としては八重咲きのものや、濃い紅色のもの、薄いピンクのものもあります。
カンナ
明治時代末期に、ヨーロッパ経由で日本へ伝来した植物です。
元々日本では素朴な花だったが、
現在の品種の多くは1850年頃からヨーロッパ諸国で様々な品種改良を経てきたもので、
ハナカンナと呼ばれています。
赤や黄色。白など花色の変化に富んでいます。
ナナカマド
バラ科の落葉広葉植物です。
初夏になると枝先に白い小花を咲かせ、秋になると広葉し、
真っ赤な赤い身がふさになって実ります。
材が硬く七度(7回)竃に入れても燃え残るほど、
燃えにくい木の例えとしてこの名前がついたそうです。
春に芽を出し、新緑、初夏の花、秋の紅葉、
雪中に映える赤い実と四季を通して楽しめるため、
盆栽や生け花にも人気が高いです。
この季節の生き物
雁(ガン・かり)
10月の初めごろに北の国から渡ってきて、
沼や湖などで冬を越す水鳥です。家族を単位とし、
隊列を組んで飛ぶ姿はつい目を奪われます。
つがいの結束が強く、
一方が死ぬまではその結びつきが切れることはありません。
カモ科ですが、鴨よりは大きく白鳥よりは小さい鳥です。
「初雁」「雁渡る」「雁来る」「雁渡し」は秋の季語とされています。
キリギリス
キリギリスは秋の虫のイメージがありますが、
実は6月〜9月頃に多く見られます。
メスには長い産卵菅があり、地中に卵を産みます。
その卵は翌年または2年目にかえります。
キリギリスは別名を機織り虫といい、
鳴く時に「ギーッチョン、ギーッチョン」という様子が
機織り機のように聞こえるからだと言われています。
近づくと隠れてしまうので、捕まえるのは難しいですが、
玉ねぎを餌にした釣りで捕まることがあります。
コオロギ
成虫は体が黒っぽい茶色をしており、8〜11月頃に見られます。
ほとんどが夜行性で。
昼間は草むらや枯葉の下でじっとしていることが多く、
夜になるとリーリーリーと優しく美しい声で鳴きます。
万葉集が編纂された平安時代から室町時代の頃には、
蟋蟀とは秋に鳴く虫の総称だったようです。
アジアの一部地域では食用にもされています。
ツグミ
全長は約24cmほど、シベリア地方から大きな群れで飛来する冬鳥です。
日本につくと群れを解いて、水田の刈跡や低い山の林、
瓦など広々とした背の低い草地に散らばって生息します。
3月になると、また群れて北へと帰っていきます。
冬に鳴かないことから「口をつぐむ」で「ツグミ」という名前になったと
言われていわれています。
この季節の行事やオススメ
鹿の角切り
10月初旬
奈良県春日大社山道脇の鹿苑で行われる行事です。
江戸時代から約340年に渡り、鹿と奈良の人々との共生の中で受け継がれてきました。
角の生えたオスの鹿は、秋になると発情期を迎え、気性が荒くなります。
そのため通行人や他の鹿を汚させないようにと、鹿の角切りが始まりました。
鹿は神様のお使い「神鹿」とされたことから、
切られた角は神前に供えられます。
オスの角は毎年生え変わるので、角を切ってもまたすぐに生えてきます。
十三夜
旧暦9月13日
十五夜である旧暦の8月15日に「中秋の名月」を眺めた後は、
旧暦9月13日の十三夜も楽しむことが風流だとされてきました。
これら二つを合わせて「二夜の月」と言いますが、
もし十三夜を見逃してしまうと「片見月(片月見)」と言って、
縁起が良くないこととされました。
鞍馬の火祭
10月22日
今宮やすらい祭・太秦の牛祭と並び、「京都三大奇祭」と呼ばれるお祭りです。
940年に、それまで御所で祀られていた由岐大明神が鞍馬に勧請された時に、
村人が地主神である八所明神を神輿に乗せ、
無数の松明を持って出迎えたという故事に由来するといわれています。
青年たちが「サイレヤ、サイリョ」の掛け声とともに、
かがり火を焚いた街中を松明を持って練り歩く姿は圧巻で、
最後に鞍馬寺の山門前にひしめき合います。
蔵王連峰(ざおれんぽう)の紅葉
9月下旬〜10月中旬
宮城県と山形県の南北にまたがる山々を蔵王連峰と呼びます。
蔵王連峰を東西に横断する山岳観光道路、
蔵王エコーラインをドライブして車の窓から道の両側に広がる極上の紅葉を愉しめます。
そして蔵王エコーラインにある「滝見台」からは、
紅葉の中を流れる日本の滝百選に選ばれた「三階(さんかい)滝」や
「不動(ふどう)滝」「地蔵滝」を望めます。
川越まつり
10月の第三土曜日・日曜日
埼玉県川越市のお祭りで、起源は1648年に、
当時の川越藩主であった松平伊豆守信綱が氷川神社に、
神輿・獅子頭・太鼓等を寄進し、祭礼を奨励したことが始まりと言われています。
絢爛豪華な山車が町中を曳行し、
何台もの山車が辻ですれ違う様は見物客を圧倒するスケールです。
また向かい合う数台の山車が祭囃子で盛り立てて競い合う
「曳っかわせ」もみどころで、特に夜は最高潮の盛り上がりを見せます。
written by はれる88